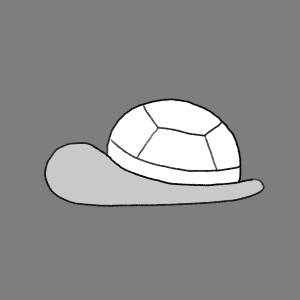お彼岸のお仏壇作法

お彼岸は春分の日と秋分の日を中日として計七日、年に2回ある先祖供養の期間です。
お彼岸の期間は極楽浄土があるとされている遥か西、真西に太陽が沈むため、ご先祖様や仏様がいる極楽浄土とこの世が一番近づく日、祈りが伝わりやすい日とされています。
彼岸入りから彼岸明けまでの1週間は、お仏壇をきれいに掃除して、お花やお線香を絶やさないようにすると良いですね!
春のお彼岸にはぼた餅(こしあん)、秋のお彼岸にはおはぎ(粒あん)を供える習慣もあります。
特別な派手さは必要なく、「ご先祖様に感謝を伝える」気持ちを持つことが一番大切です。
お盆のお仏壇作法

お盆はご先祖の霊をお迎えする大切な行事。
お仏壇の前に精霊棚(盆棚)を設けたり、盆提灯を飾ったりする地域もあります。
きゅうりとなすで馬と牛を作る、迎え火・送り火といった風習も有名ですね。
ごちそうとして季節の果物や野菜をお供えしたり、ほおずきを目印として飾ったりするお家もあるようです。
初日は長旅で疲れたご先祖様のために甘めのお餅を用意し、最終日は帰る際の手綱替わりになる素麺を用意するとよいとされています。
地域や家庭によってさまざまな特色があるのもお盆かもしれません。
命日のお仏壇作法

命日は個人を偲ぶ特別な日。
その方の好きだったお花や食べ物をお供えすると心がこもります。
ご家族で集まってお経をあげてもらったり、静かに手を合わせたりするだけでも立派な供養になります。
特に一周忌や三回忌といった節目の法要では、親族や僧侶を招いて仏壇の前で丁寧にお参りするのが一般的です。(お寺に伺って法要を行ってもらうケースもあります。)
お彼岸・お盆・命日の作法の違いを理解して丁寧に供養を

お彼岸は「ご先祖さま全体への感謝」、お盆は「ご先祖さまをお迎えする行事」、命日は「特定の方を偲ぶ日」と、それぞれ意味合いが異なります。
仏壇の作法もそれに合わせて、掃除・お供え・飾り付けなどを工夫するとより丁寧な供養になります。
ただし、形式にとらわれすぎずに「感謝と供養の心」を持つことが一番のポイントです。

◆yukari.t
葬儀社を営む家に嫁いで10年、アラサー3児の母です。
日常の中で“最期の時間”に寄り添う仕事に向き合ってきました。
そんな経験をもとに、葬儀にまつわる情報や日常マナーをお届けするライターとしても活動しています。
終活アドバイザー・終活ガイドの資格も保有しています。
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。